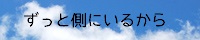
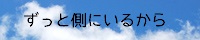
晴れ渡る青空を見上げながら、私は回想していた。
あの人と共に過ごした数年間は、今までにないくらい幸せだったと思う。きっと私は、この先それ以上の幸せを味わうことができないのだろう。けれど私は、これから確かな幸せを得る。
「どうかしたのかい? この式場は気に入らない? 他にしようか?」
隣に付き添うように経っていた彼が、心配そうに顔を覗いている。きっとまた、難しい顔をしてしまったのだろう。私は申し訳なく、苦笑しながら、彼の手を取った。
「ちょっと頭がぼーっとしてただけ。素敵な式場だね」
「そう、気に入ったならよかったよ。母が勧めてくれたんだ」
「お母様が? センスが良いんだね。とても素敵だもの」
彼は笑っている。照れ隠しなのだろうか。笑顔が多いこの人は、あの人よりも明るく、社交的だった。
(いけない、またあの人と比べてしまって……)
あの人が消えたのは、桜の咲き始めた、まだ寒さの残る頃だった。
あの人はただ一言、いつか迎えに来ると言い残して、それきり連絡を絶った。
別れたかったのなら、なぜもっとはっきり言ってくれなかったのかと、何度悩み考えても、彼から連絡が来ることも、その結論が分かることもなかった。
「―――また彼のことを考えているのかい? 僕では不満かな……」
彼には、あの人のことを、包み隠さず伝えてある。まだ割り切れない私を、それでも愛してくれている。この人の腕の中で、何度涙を流したのだろう―――何も言わずに側にいて、私を慰めてくれた彼を、裏切るようなことはできない。
「いいえ、私には、貴方しかいないから……」
語尾が震え、涙がこみ上げるのを堪えながら、私は彼の胸に飛び込んだ。彼は黙って私の背に手を回し、受け止めてくれる。何度もこの人に救われた。
「無理はしないでほしい。これが君を苦しめるなら、今すぐにでも―――」
「いいの。もう、あれは過去の話なの。たとえいまさら戻ってきたって、それは過去のことでしょ?」
「それなら、いいんだ。――――もう、離さない。あの時とは違う」
私は思わず顔を見上げた。彼は何も言わず、私を抱きしめている。その腕が少し震えていることを、私は気づいていた。
「不思議だよね、縁って。昔断ち切られたはずの輪が元に戻ったんだよ。彼に感謝すべきだろうな。君を手放すために全てを断ち切ってくれた、彼に」
「何を言っているの? どうしたの、急に……」
「僕の家がどんな家かは、知っているだろう。けれど君は、自分の家がかつてどんな家だったかは知らないんじゃないのかい?」
彼の口から出た真実は、今まで知らされたことのない、けれどどこかで分かっていたことだった。 父の家はかつて裕福だった。父の父―――私の祖父が事業に大失敗し、会社が倒産するまで、父とは母は裕福な暮らしをしていた。もちろん、その頃生まれた私も。
そして私には―――許婚がいた。彼という、生まれたときから決められた相手。けれど、父の会社の倒産で、その話は消えてなくなった。繋がった縁は、一つの輪は、無残にも二つに引き裂かれてしまった。
彼はそのとき何も思っていなかったという。当然だろう、お互いにまだ赤子で、会ったこともなかったのだから。
けれど新しく許婚が決まって、大人になり、本当は別に居たのだと聞かされたとき、彼はどうしても私を知りたくなったという。もちろんそのときは、こんなことになるとは思ってもいなかったし、それをお母様が認めてくれるとは思っていなかったそうだ。
「―――父はあまり世間体を気にしない人でね。母さえ納得すればいいと思っていた。君の姿を初めて見たとき、どうしてもほしくなった。たとえそれが、僕にとって弟といえるくらいの存在である、執事の恋人でも」
「あの人が……あなたの執事? そんな、なぜそんなことを隠していたの?」
「分かっているよ、これが僕のわがままだということは。けれどそれでも、君を忘れられなかったんだ。彼のためにいくら忘れようとしたことか」
違う、明かして欲しかったのは、そのことではない。
ずっと知りたかったのは、あの人のことではないのに。
「違うの。私が知りたかったのは、あの人のことじゃない。貴方のこと」
「僕のこと?」
「そう。この出会いが偶然でないだけで、私は十分幸せだよ」
ずっと心の中にあった靄が、取れた気がした。彼はずっと自分を見ていてくれた。ずっと思えきれずにいた私を、受け入れてくれる。
(これ以上の幸せはないよね、きっと)
彼の背に腕を回して、彼の耳元に囁いた。
「今までありがとう。これから、よろしくお願いします」
そっと腕を離し微笑むと、彼は驚いている。そんな彼の様子が可笑しくて、私は再び笑みを零した。