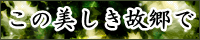
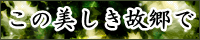
見渡す限り青々とした木々と、静かに流れる川の水。毎年夏に見れる蛍が、私は好きだった。
今ではあまり見なくなってしまった彼らが、ここにだけはあるのが、誇りだった。
ただし今の季節は12月末。年末ですっかり辺り一面真っ白である。しっかりと寒さ対策をしても、寒いものは寒い。
「沙耶、どうしたんだい。まさか、真冬に川に入るつもりじゃないだろうね。もどってきなさい」
川は家が建つ場所よりも少し低い場所を流れており、川の近くに行くにはまるで崖のような土手から、石の階段を下りなければならない。土手に腰掛けて迷っていた私を、祖母が呼びとめた。
「ここは他所に比べて気温が低いんだよ。夏は涼しいが、冬は寒いからね」
もうクリスマスも過ぎ、すっかり冬景色が広がっている。ただ今年は暖冬だからか、思ったよりも雪は積もっていなかった。
ここは昔から少し気温が低い土地で、夏は涼しいが、冬は寒かった。けれど今年の冬はそうでもないらしい。
冬が暖かくなるのは過ごしやすくてよいが、夏が暑くなるのは困る。このまま年々温暖化が進むと祖父母も暮らしずらくなるかもしれないと、私は思った。
「流石に寒いから、中には入らないよ。でも、近くで見たくって」
「階段も、ちょっと雪が積もって危ないから、やめておきなさい。ただでさえ急な階段で危ないんだから」
「そうだね、そうする」
少々祖母が大げさな気もするが、確かに階段は横幅も狭く、雪が降っていない日でも慎重に降りるような造りだ。それくらい用心した方がいいだろう。
すっと立ち上がると、私は少し伸びをして、家に向かって歩き出した。
ここは祖父母が静かに暮らす田舎町。周囲にはもう若い人は住んでいない。殆どの人が年金暮らしで、自分達の食べる野菜を育てたりしながら、のどかな毎日を過ごしている。
そんなこの地に、私が戻ってきたのには、理由があった。
「ねぇ、理由、聞かないの? 勝手に押しかけてきて」
「聞く必要があったかい? 若い孫一人養えないほど、貧乏な暮らしはしてないよ。それに働き手が増えて助かってるくらいさ」
「でも……」
祖母は私に背を向けたまま、こちらを見ようとはしない。昔から、私は祖母が振り返るのを見たことがない気がする。いつも真っ直ぐ前を見つめている人だった。
そんな強さが好きで、いつも甘えてばかりだ。一方で、祖母は決して私たちに甘えないし、弱さを見せない。そんな祖母を尊敬していた。
祖母は決して逃げない人だから。自分はいつまで経ってもとてもそんな強くはなれなくて、大人になって祖母の偉大さを知った。
「沙耶。私だってね、今と昔とじゃ全く違うんだってことくらい分かるんだよ」
「うん」
「だからね、こんな田舎町に逃げたくなるようなことがあったんだろう。きっと、私たちにも言いたくないようなことが。それを無理に聞こうなんて、そんな不躾なことはできないってこと」
背中を見せたままの、祖母の表情は汲み取ることは出来ない。けれどきっと、とても優しい表情なのだろうと思う。いつだって祖母は優しい笑みを浮かべていて、怒ることも殆どなかった。母が甘やかしすぎだというくらい、昔から優しい人だった。
「おばあちゃん。私、もう帰りたくない。ずっとここで暮らしたいよ」
「それはダメだよ、沙耶。言っただろう。今と昔とじゃ全く違うんだから」
「でも、もうやっていけないよ。信じていた人に裏切られたの。嫌な思い出しかないあの場所に、戻りたくない」
ずっと一緒になることだけを支えにしてきた。そのために辛い仕事も乗り越えてきたし、お金も貯めてきた。けれど全て意味がなくなってしまった。もう辛い仕事を頑張る意味も、お金を貯める理由もなくなったのだ。
たったそれだけのことで折れてしまう私は、弱いのだと思う。祖母だったらきっと笑って忘れられるのかもしれない。そんな心の強さを、祖母は持っているから。
「それなら、また違う場所でやっていけばいいじゃないか」
「でも、違う場所なんて」
「確かじいさんの甥が、北の方にいたはずさ。最近会社を立ち上げて人手が足りないって言ってたけど。行ってみる?」
滅多に振り向かない祖母が、悪戯な表情を浮かべて振り向いた。その表情はどこか優しく、私は思わず涙を零した。冷たいものが頬を伝い、祖母が少し乱暴にそれを拭った。
「……行く。行きたい」
「だってさ、じいさん、ちょいと電話してやって」
「あそこの奥さん、ずっと娘を欲しがってたから、きっと喜ぶさ」
祖父はそう陽気に答えて、早速家の中へ駆け込んでいった。嬉しそうに受話器を耳に当てる祖父の様子が思い浮かぶ。
「別に無理して同じところで暮らす必要は無いんだよ。お前は自由なんだ。どこへだって行けばいい。帰る場所はここにあるからね」
私だって、若い頃はそうして逃げ回って、じいさんに会ったんだから。
そう語った祖母の表情は、今までにないくらい、輝いていた。